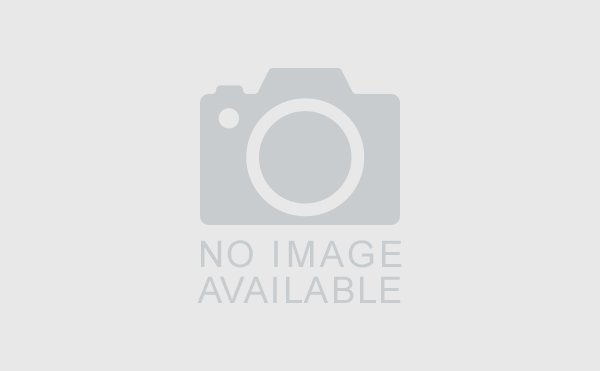「なぜ売れた?なぜ売れない?」を説明できる消費者行動モデル入門
今日の記事はこんな悩みをお持ちの方に向けてのものです。
- 消費者行動モデル(AIDMA・AISASなど)は聞いたことあるけど、違いが分からない
- 広告やキャンペーンの効果を「感覚」ではなく理論的に説明できるようになりたい
- 上司やクライアントに根拠をもって施策を提案したい
- 消費者がどうやって商品を知り、買うまでに至るのかを体系的に理解したい
- 教科書的な説明は読んだけど、実務にどう落とし込めばいいのか分からない
- そもそもどのモデルを使えば自社の商品やサービスに合うのか悩んでいる
- 「結局どれを覚えておけば仕事で役立つの?」と整理できずに困っている
そしてもしあなたが、
- 売上や成果の理由をちゃんと言語化できるようにしたい。
- 企画や施策に説得力を持たせて、上司やクライアントに説明できるようにしたい
- やみくもにフレームワークを当てはめるのではなく、
ちゃんと根拠をもって最適なフレームワークを選びたい - 自社の商品・サービスの顧客の購買プロセスのどこに問題があるのか、
しっかりと把握したい
と思うなら、この記事を読んでください。
運任せの広告運用・・・
僕はこの会社で広告の運用を任されている。
それまで一度もそんな経験はないのにいきなり任されてしまった。
毎朝PCを立ち上げるたびに胸がざわめく。
画面には広告の結果が表示されている。
「また反応が下がってる・・・」
しかし理由がさっぱりわからない。
広告文を変えたり、
バナーの色を変えたり、
流行りのSNS広告を試したり・・・
いろんな手段を試したが、それでもだめだった。
それでも何かしらの理由を上司に説明しないといけない。
「多分、タイミングが悪かったんじゃないかと」
「・・・お客さんの気分・・・ですかね?」
自分でも答えになっていない、どうしようもない理由ばっかりが口から出てくる。
いったい何が原因なのだろうか?
問題の原因は?
彼の問題の原因は何なのでしょうか?
いくつも原因はあるでしょうが、
一つ上げるとするなら、
そもそもどこを集中的に広告運用していけばいいのかわかっていない、
つまりボトルネックを特定する術を持っていないことが原因に挙げられるでしょう。
例えば流行りのSNS広告に手をだしたりしたようですが、
これなどはとにかく流行っているから導入してみた、
という戦略的でないアプローチの典型です。
戦略的であるとは、
自社の限りあるリソース(資源)をどこに投入するのかの基準をもっていることです。
こうした基準がないまま流行りもの、
効果があるとされているものを手あたり次第導入するから、
効果があるのかないのかわからないのです。
そもそもその「効果」がというのが、
どんな効果なのかを把握しないまま導入している、
というのが実情でしょう。
多くの場合、
広告を打ちだす=売り上げを出す
という図式になっています。
しかし実は売り上げを出すまでにはいくつかの段階があります。
一例としてこのような順番があります。
- まず注意をひかれる
- 問題を認識する
- 商品・サービスを欲しいと思う
- 比較検討する
- お問合せする
- 購入する
このような段階を経て、消費者は行動、つまり購入をします。
これを消費者行動モデルと言います。
広告はこの各段階に合わせたものにしなければいけません。
例えば商品どころか自分が問題を抱えているとも思っていない人に、
商品を案内しても無意味です。
一例としてダイエット商品を挙げてみましょう。
ダイエット商品を買う人の購買心理の変遷
実はダイエット商品は太っている人よりも、
痩せている人のほうが売りやすいです。
正確にはすでにダイエットに取り組んでいる人です。
なぜなら、太っていることが問題だと思っているからです。
太っているままの人にダイエット商品を勧めても、
その人は反応しません。
なぜなら、もしかしたら口では「痩せたい」と言っているかもしれませんが、
そのために行動したいと思っていないからです。
そういう人にはまず太っていることが問題であると認識させなければいけません。
つまり、いきなり商品を売り込むのではなく、
商品が必要な理由を伝える無料レポートなりを提供しなければいけない、
ということです。
そしてすでにダイエット商品をいくつも試している人、
そのような人に対しては、競合よりも自社の商品が優っていることをアピールするべきです。
そのような人に今さら「ダイエットをしなければいけない理由」などを伝えたところで、
「知ってるよ」と見切られて終わります。
だから競合との差別化により、
自社の商品を選ぶ理由を与えてあげなければいけないのです。
とはいえ現代は差別化の難しい時代ですからそう簡単にはいきませんが。
そうして自社の商品の特徴を知り、
念のためにもう少し知りたいなと思った見込み客が、
お問合せをして、十分な情報を仕入れます。
そうして初めて購買へと至るのです。
こうした各段階にあったアプローチが必要だと知っているかいないかで、
広告の打ち出し方というのは変わります。
そもそも各段階ごとで求めるものが違うのです。
その広告で単純に認知してもらいたいのか?
その広告でお問合せまでしてもらいたいのか?
その広告でお得な情報を提供しているチャンネルに登録してもらいたいのか?
その広告で一気に購買までしてもらいたいのか?
広告のゴールは単純に購買してもらえればいいというだけではありません。
その広告を見る人の心理状態に合わせたゴールがあります。
なぜこのように分ける必要があるか?
このように消費者行動モデルを知らない事業者はみな、
今すぐ購入する気のある見込み客に対してばかり売り込みをしています
しかし自社にとって非常に魅力的な見込み客は、
たいていの場合、他社にとっても非常に魅力的です。
よって、競争が激しくなり、
広告費が激増します。
それは利益を圧迫し、価格競争へと突入させるでしょう。
しかし現代はあまりに多くの商品があるために、
注目を集めるのが難しくなっています。
目立とうとすれば、必然的にそれだけ広告費が増大するしかなくなるのです。
当然広告費に潤沢に資金を投入できるのは大企業くらいなものです。
よって、中小企業は効率的に広告費を投入しなければなりません。
具体的には競争の激しい、今すぐ購入する気のある見込み客、
言い換えれば、「今すぐ客」を追い求めるのはやめましょう。
そうではなく、まだ購入しようと思っていない見込み客、
言い換えれば、「そのうち客」をどうやって引き込めるかを考えるべきです。
購入する気のない見込み客を、
どうやってシステマチックに購買しようと思うまで育て上げることができるのか?
そのフレームワークとして有効なのが、
消費者行動モデルです。
では紹介していきましょう。
購入までの道のりを知る:消費者行動モデルの全体像
広告運用の「ボトルネック」特定に不可欠
前述の通り、広告運用で成果が出ない原因の多くは、「どこにリソースを集中すべきか」というボトルネックが特定できていないことにあります。
- 認知度が低いのに、いきなり「いますぐ購入!」の広告ばかり打っていないか?
- 商品への関心は高いが、競合との比較で負けているのに、商品の説明を繰り返していないか?
消費者行動モデルは、この「どこに問題があるのか?」を特定するための分析軸を与えてくれます。
消費者行動モデルの基本的な流れ
消費者行動モデルには数々の種類があります。
しかし、ほとんどの消費者行動モデルは、以下の3つのフェーズをベースに構成されています。
| フェーズ | 顧客の主な心理状態 | 企業が目指すゴール |
| 認知・関心 | 商品や問題の存在を知る段階。「知る」「興味を持つ」 | 認知度の向上、問題提起 |
| 比較・検討 | 情報を集め、他社製品と比較する段階。「調べる」「欲しいと思う」 | 競合との優位性をアピール |
| 購買・行動 | 最終的な決定を下し、購入に至る段階。「買う」「試す」 | 契約、購入、申し込み |
もちろんこの3つにプラスして、時代に合った様々な段階があります。
が、基本はこの3つのフェーズが抑えられていれば消費者行動モデルを使いこなすことができるでしょう。
(逆に言えばこの3つのフェースを抑えずに枝葉の部分を習得しても事業に与える影響は大きくはないでしょう
では早速、次章ではこのモデルの代表格である「AIDMA」と「AISAS」を取り上げ、それぞれの違いと、現代ビジネスにおける意味合いを詳しく見ていきましょう。
承知いたしました。続いての見出し案「代表的な消費者行動モデルの比較と使い分け」のドラフトを作成します。
代表的な消費者行動モデルの比較と使い分け
消費者行動モデルは時代と共に進化してきました。
ここでは、古典的なモデルから現代の主流モデルまで、代表的なものを比較し、それぞれがどのような購買プロセスを捉えているのかを解説します。
消費者行動モデルの原型:【AIDA(アイダ)】
AIDAは、約100年以上前の1898年にアメリカのE・S・ルイスによって提唱された、世界で最も古い消費者行動モデルです。
これは、顧客が広告やプロモーションに触れてから、最終的に購買行動を起こすまでの、人間心理の最も基本的な変遷を4段階で捉えたものです。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 企業・広告の役割 |
| A | 注意 | Attention | 広告や情報に「気づく」 | 顧客の注意を引く |
| I | 関心 | Interest | 商品やサービスに「興味を持つ」 | 興味を持続させる |
| D | 欲求 | Desire | 「欲しい」「使いたい」と「強く思う」 | 感情的な欲求を高める |
| A | 行動 | Action | 実際に「購入する」 | 購買行動を促す |
Google スプレッドシートにエクスポート
AIDAモデルの重要なポイント
1. シンプルさと普遍性
AIDAモデルは極めてシンプルであるため、どんな商品やサービス、媒体(マスメディア、デジタル広告、営業トークなど)にも適用できる普遍的なフレームワークです。現代のデジタルモデル(AISASやDECAX)も、基本的にはこのAIDAの4要素を核として、間に「検索」や「共有」といった時代に合わせた行動を挟み込んでいるにすぎません。
2. 短期的な成果に焦点を当てる
AIDAは、消費者が広告に触れてから「その場ですぐ行動を起こす(Action)」までのプロセスを重視しています。そのため、即効性のあるプロモーションや営業におけるクロージングの設計図として特に有効です。
- Attention(注意):キャッチコピーやアイキャッチ画像で目を引く。
- Interest(関心):ターゲット顧客が持つメリットを具体的に提示する。
- Desire(欲求):「この商品がないと困る」という感情的な欲求を刺激する。
- Action(行動):「今すぐ電話」「こちらから購入」といった具体的な行動を指示する。
マスメディア時代の古典:【AIDMA(アイドマ)】
「AIDMA」は、テレビや新聞、雑誌などのマスメディアが情報伝達の主役だった時代に誕生した、最も基本的な消費者行動モデルです。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 企業・広告の役割 |
| A | 注意 | Attention | 広告や情報に気づく | 認知の獲得 |
| I | 関心 | Interest | 興味・関心を抱く | 商品の魅力付け |
| D | 欲求 | Desire | 「欲しい」という欲求が高まる | 感情的な訴求 |
| M | 記憶 | Memory | 購買直前まで商品を覚えている | リマインド、ブランドの定着 |
| A | 行動 | Action | 実際に商品を購入する | 購買の促進 |
AIDMAの活用シーン
AIDMAは、今でもブランド認知を広げたいマス向けのキャンペーンや、衝動買いに近い商品(低価格帯の日用品など)の行動設計の基礎として使えます。特に、インターネットでの情報検索や共有のプロセスが含まれていないため、消費者の「記憶」をいかに維持させるかに焦点を当てた広告戦略を立てる際に役立ちます。
インターネット時代の標準モデル:【AISAS(アイサス)】
2000年代に入り、インターネットが普及すると、消費者の行動に大きな変化が起きました。それが「検索」と「共有」です。この変化を捉えて、電通が提唱したのが「AISAS」モデルです。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 特徴的な変化 |
| A | 注意 | Attention | 広告や情報に気づく | AIDMAと同じ |
| I | 関心 | Interest | 興味・関心を抱く | AIDMAと同じ |
| S | 検索 | Search | 自分で情報を検索する | 新しい行動 |
| A | 行動 | Action | 実際に商品を購入する | AIDMAの「行動」と同じ |
| S | 共有 | Share | 使用感や感想を共有する | 新しい行動 |
AISASの活用シーン
AISASは、現代のデジタルマーケティングの基礎中の基礎と言えます。特に高額な商品や検討期間が長い商品、口コミが重要な商品(化粧品、旅行、家電など)の戦略を立てる際に必須です。
- Search(検索):SEO対策、リスティング広告、コンテンツマーケティングなど、「興味を持った顧客」を確実に自社サイトへ誘導する施策に力を入れるべきです。
- Share(共有):購入後の満足度を高め、SNSやレビューサイトで好意的な情報を発信してもらうための施策(サンクスメール、レビュー特典など)が重要になります。
インターネットは、SNSの登場によりさらに進化します。
続いてはSNSの登場で発生したモデルを紹介します。
SNS時代の消費者行動モデル:VISAS、SIPS、ULSSAS
SNSの普及は、消費者行動に「検索」と「共有」だけでなく、「視覚(Visual)」や「共感」、「拡散」という要素を強くもたらしました。これに対応する3つの代表的なモデルを比較解説します。
1. 視覚と口コミを重視:【VISAS(ヴィザス)】
VISASは、AISASの「検索(Search)」と「共有(Share)」を、InstagramやYouTubeなどの視覚的要素が強いメディアでの行動に置き換えて生まれたモデルです。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 特徴的な変化 |
| V | 視覚 | Visual | 写真や動画で商品・情報に魅了される | Attention(注意)の発生源が視覚情報に |
| I | 衝動 | Impulse | 視覚的な魅力により、衝動的な購買意欲が高まる | Desire(欲求)が瞬間的・感情的に発生 |
| S | 検索 | Search | 購入前に詳細をハッシュタグなどで検索する | SNS内検索が重視される |
| A | 行動 | Action | 実際に商品を購入する | 購買 |
| S | 共有 | Share | 購入した体験を写真や動画で共有する | **次のV(Visual)**へと繋がる |
VISASの活用シーン
「映え」や動画コンテンツが重要な商材(化粧品、食品、旅行、ファッション)に最適です。購買意欲が**「理性」よりも「感情」や「視覚」**に強く依存するプロセスを捉えています。
- Visual(視覚):広告やパッケージが写真や動画で魅力的に映るよう設計する必要があります。
- Impulse(衝動):限定性や希少性を訴求し、衝動的な購入を後押しする施策が効果的です。
2. 共感と参加が鍵:【SIPS(シップス)】
SIPSは、SNSで誰かの投稿に共感し、自ら参加することで購買に至るプロセスを捉えています。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 最適な施策 |
| S | 共感 | Sympathize | 友人やインフルエンサーの情報に共感する | 顧客の興味関心に寄り添ったストーリー性のある発信 |
| I | 確認・識別 | Identify | 共感した情報が自分に合うか確認する | ターゲティングの明確化、メリットの言語化 |
| P | 参加 | Participate | コメント、いいね、リツイートなどで関わる | ハッシュタグキャンペーンなど顧客参加型企画 |
| S | 拡散・共有 | Share & Propagate | 自身の経験や感想をSNSで発信する | 質の高いUGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出 |
3. 拡散のサイクルを重視:【ULSSAS(ウルサス)】
ULSSASは、**ユーザー投稿(UGC)を認知の起点とし、購買後の拡散までが次の購買を生むサイクル(ループ)**を強調しています。
| 略称 | 日本語 | 英語(頭文字) | 顧客の行動(心理) | 最適な施策 |
| U | ユーザー生成 | User Generated Content | 友人・知人の投稿(UGC)を見て商品を知る | UGCを活かした二次利用、インフルエンサーマーケティング |
| L | Like! | Like! | 投稿にポジティブな反応を示す | SNS上でのコミュニケーション最適化 |
| S | 検索(SNS) | Search(SNS) | ハッシュタグ検索やアカウント検索で情報を深掘りする | SNS内のアカウント設計とハッシュタグ戦略 |
| S | 検索(一般) | Search(General) | Web検索で情報を確認する | SEO対策、リスティング広告 |
| A | 行動 | Action | 実際に商品を購入する | 購買 |
| S | 拡散 | Spread | 自身の体験をSNSに投稿してUGCを生み出す | 投稿したくなる体験設計(パッケージ、特典など) |
4. SNSモデルの使い分け
SNS関連のモデルは、**「認知の起点」と「購買の動機」**で使い分けます。
| モデル名 | 認知の起点(最初のAやS) | 購買の動機 | 最適な商品・施策 |
| VISAS | Visual(魅力的な画像・動画) | Impulse(視覚による衝動) | ビジュアルの訴求力が決め手となる商材(コスメ、グルメ) |
| SIPS | Sympathize(共感、話題性) | Participate(関わりたいという欲求) | コミュニティ性やブランドへの共感が重要な商材 |
| ULSSAS | UGC(ユーザーの実際の投稿) | Like!(ポジティブな評価) | 口コミの量と質が重要で、拡散のサイクルを回したい商材 |
あなたの商材が、「視覚的な魅力」で衝動買いさせるべきか、「共感」を軸にファンを増やすべきか、あるいは**「口コミ」を連鎖させる設計**を重視すべきか、によって最適なモデルを選び、広告のゴールを設定してください。
その他の代表的なモデル(DECAXなど)
DECAXの特徴
DECAXは、顧客が自ら情報を探し、購入に至る現代の購買行動をより深く捉えています。
- Discovery(発見):SNSやオウンドメディアなど、広告以外の場所で偶然商品やコンテンツと出会うことを指します。
- Engage(関係構築):この段階で、企業は良質なコンテンツを通じて顧客の疑問や悩みに答え、信頼関係を築く必要があります。いきなり商品を売るのではなく、まずファンになってもらうためのアプローチが重要です。
- Xperience(体験・改善):購入後の満足度を可視化し、顧客の声をコンテンツに反映させることで、次のDiscoveryを生み出す循環(サイクル)を形成することを目指します。
AMTULの特徴
AMTULは、購入後の行動に重きを置いています。特に、**L(Loyalty:固定客化)**に至るまでの道筋を細かく分析するのに適しています。
- Trial(試用):本契約の前に、サンプルやお試し期間を利用してもらうプロセスは、継続利用型ビジネスにおいて極めて重要です。
- Usage(本格利用):一度購入・契約しても、使われなければ解約(チャーン)に繋がります。このモデルでは、継続的に**「使ってもらう」**ためのサポート施策(オンボーディング、活用セミナーなど)を設計するのに役立ちます。
DECAXとAMTULの比較表
| 項目 | DECAX(デキャックス) | AMTUL(アムトゥル) |
| 提唱者 | 電通 | 広告会社(主に継続利用の分析に使用) |
| 誕生背景 | コンテンツマーケティング、オウンドメディアの普及 | サブスクリプションなど、継続利用型ビジネスの増加 |
| 最も重視すること | 顧客との関係性構築と維持 | 継続利用・定着(ロイヤリティ) |
| 主な活用分野 | オウンドメディア、ブログ、SNS運用、情報商材 | サブスクリプションサービス、BtoB、化粧品などのリピート商材 |
| 行動プロセス | Discovery(発見) → Engage(関係構築) → Check(確認・検討) → Action(行動・購入) → Xperience(体験・改善) | Awareness(認知) → Memory(記憶) → Trial(試用) → Usage(本格利用) → Loyalty(固定客化) |
| プロセスの特徴 | **「発見(D)」と「体験(X)」を重視。企業からの情報提供で顧客に自ら課題を「発見」させ、購入後も「体験」**を共有・改善してもらうまでを設計する。 | 「試用(T)」と「本格利用(U)」を重視。特に購入後の定着とロイヤリティの形成プロセスを詳細に分析する。 |
| 広告・施策のゴール例 | 無料レポートのダウンロード、メールマガジン登録、定期的なコンテンツ閲覧 | お試しセットの購入、無料期間の利用、アプリの継続利用、リピート購入 |
全消費者行動モデルの比較と使い分け
1. モデル別:購買プロセスの特徴と分類
消費者行動モデルは、その誕生背景となる時代や購買後に何を重視するかによって大きく3つのグループに分類できます。
| グループ | 代表的なモデル | 顧客行動の鍵となる要素 | 最適な活用シーン |
| 古典・マス広告系 | AIDA, AIDMA | 記憶(Memory) | 短期的な購入促進、テレビ・雑誌などマスメディアでの認知拡大 |
| Web・デジタル系 | AISAS, DECAX | 検索(Search)、関係構築(Engage) | 情報収集が必須な商材、オウンドメディアやSEO戦略 |
| SNS・リピート系 | VISAS, SIPS, AMTUL | 視覚(Visual)、共感(Sympathize)、継続(Loyalty) | 映え商材、コミュニティ形成、サブスクリプションなどLTV重視ビジネス |
2. 主要モデルの比較一覧と使い分けの指針
特に重要な5モデル(AISAS、VISAS、SIPS、DECAX、AMTUL)を中心に、それぞれの**「認知の起点」と「購買後の行動」**を比較することで、最適なモデルを選びます。
| モデル名 | 認知の起点(最初の要素) | 購買の決定打となる要素 | 購買後の行動 | 最適なビジネスシーン |
| AISAS | Attention(広告・情報) | Search(Web検索による情報確認) | Share(口コミ投稿) | 検討期間が標準的な一般的なECサイト、Web広告戦略全般 |
| VISAS | Visual(魅力的な画像・動画) | Impulse(視覚による衝動) | Share(映える写真・動画の投稿) | **「映え」**が命となるコスメ、食品、ファッション、旅行など |
| SIPS | Sympathize(友人・インフルエンサーの情報への共感) | Participate(キャンペーンなどへの参加意欲) | Share(ストーリー性のある拡散) | 若年層向け商材、共感を軸としたブランディング、コミュニティ形成 |
| DECAX | Discovery(オウンドメディア等での問題発見) | Check(記事やコンテンツによる検討) | eXperience(体験共有と改善) | コンテンツマーケティング、情報商材、ナーチャリング(顧客育成) |
| AMTUL | Awareness(認知) | Trial(試用) | Usage(本格利用) | サブスクリプション、BtoBサービス、リピート購入を前提とした商材 |
3. 実務におけるモデル選択の考え方
どのモデルを使うべきかは、**「自社の売上がどこで決まるか」**という視点で選択します。
| 選択の視点 | 解決したい課題 | 推奨モデル |
| 即効性 | 短期的な売上を上げたい、即座に購入してほしい | AIDA / AIDMA |
| 情報収集 | 競合との比較に勝って購入してもらいたい | AISAS |
| SNSの活用 | SNSでの話題性やビジュアルで集客したい | VISAS / SIPS |
| LTV | 一度きりではなく、長く継続的に利用してもらいたい | AMTUL |
| 顧客育成 | 潜在顧客に時間をかけて商品の必要性を理解してもらいたい | DECAX |
モデルを使いこなすためのヒント:複合的なアプローチ
現代の消費行動は複雑なため、一つのモデルだけで完結することは稀です。例えば、アパレルブランドの場合、
- VISASでInstagramから**「衝動的」**に認知を獲得し(V
I)。
- 興味を持った顧客はGoogleで**「Web検索」**し(AISASのS)。
- 購入後、満足した顧客は継続的に利用するために**「メルマガに登録」**する(DECAXのE)。
といったように、複数のモデルの要素を組み合わせることで、より正確に顧客の行動を捉えることができます。重要なのは、「運任せ」ではなく、自社の商品にとって**最適な「ボトルネック(離脱ポイント)」を発見するための論理的な「ものさし」**としてモデルを活用することです。